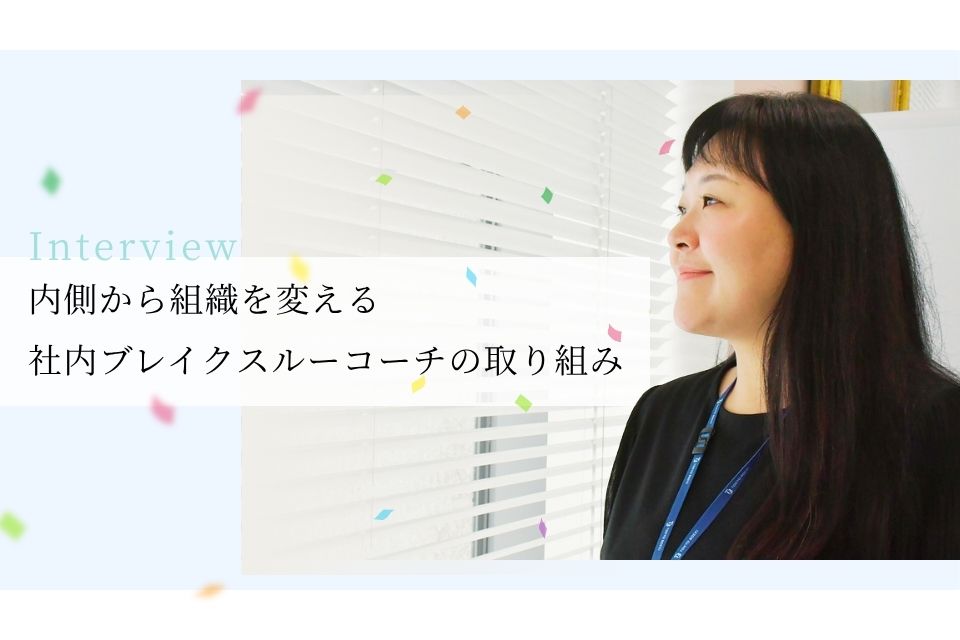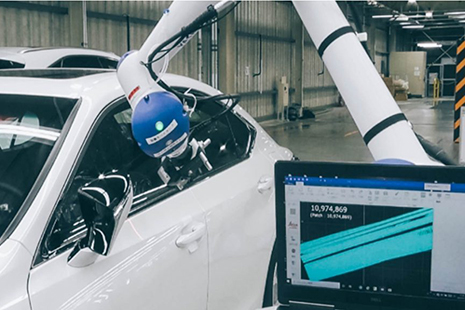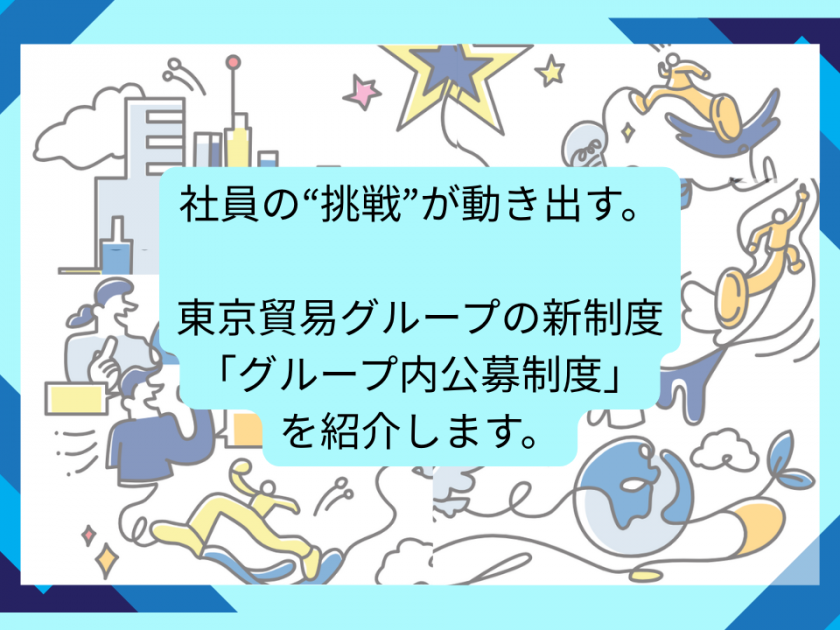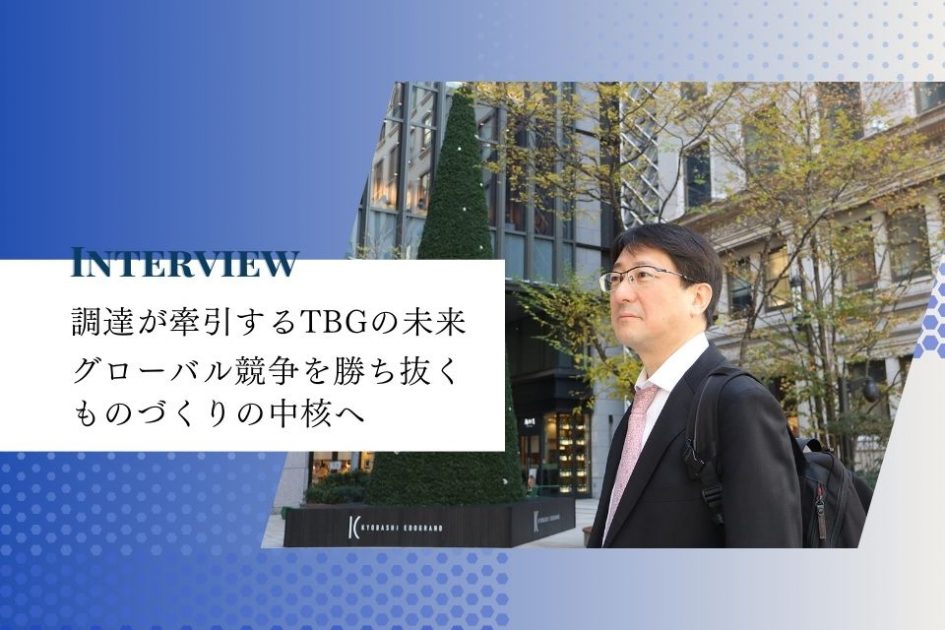社員インタビュー:内側から組織を変える社内ブレイクスルーコーチの取り組み
社員1人1人の意識と行動を変え、会社を変革していく。このビジョンのもと東京貿易テクノシステム(TTS)は、「社内ブレイクスルー・コーチ養成プログラム」という取り組みを始動。その一期生として手を挙げたマーケティング部営業企画チームのメンバーを紹介します。
1年間に渡るプログラムの中で彼女が掴んだのは、単なる“スキル”ではない。自分自身の仕事への向き合い方、周囲の力を引き出す姿勢。会社を大きく前進させる原動力を身に付けた。その学びは、全社を横断するエリアミーティングの場も一新するほど、確かな変化をもたらしている。
1年間の学びと、初の実践を経て得た手応え。その軌跡を辿ると、個人の成長と組織の変革が重なって見えてきた。
-
PROFILE

東京貿易テクノシステム株式会社
マーケティング部 営業企画チーム チームリーダー
2012年中途入社。海外パートナーとの連携やデータ分析による営業支援・効率化の推進など、幅広い業務を担う。2024年には「社内ブレイクスルー・コーチ養成プログラム」に一期生としてプログラムに参加。翌年からはエリアミーティングのファシリテーターとしての役割も担う。「問題はチャンス」を合言葉に、チームと個人の成長を支えることを目指している。
目次
・変化は、自分の中から始まった
・空気を変える、人を動かす
・前向きな連鎖が、組織を変えていく
・コラム|心と体をととのえる、アロマ習慣
・取材を終えて|グループ広報部より
変化は、自分の中から始まった
「心のざわめき」が背中を押した──社内公募への直感
「見た瞬間、不思議と心がざわついたんです。」
彼女が「社内ブレイクスルー・コーチ養成プログラム」の存在を知ったのは、2024年春のこと。TTSでは水原社長の就任を契機に、“ソリューション型営業”へのシフトが掲げられ、業務に対する意識変革と組織全体の対話力強化が急務となっていた。そこで導入されたのが、外部コーチによる「ブレイクスルーセッション」だった。
当初は経営層を対象に始まった取り組みだったが、セッションを受けた役員の手応えは大きく、やがて対象はチームリーダー層へと拡大される。こうして立ち上がったのが、社内にコーチを育成する第1期生制度「社内ブレイクスルー・コーチ養成プログラム」だった。
社内ブレイクスルーコーチ(IBC)とは、社内でのコーチングを通じて、社員が主体的に問題解決やプロセスチェンジを行うためのスキルを身につけるプログラムです。具体的には、コーチングのセッションを通じて、ファシリテーションスキルや問題解決能力を学び、社内でのブレイクスルーを促進する役割を担います。
「この募集を見た瞬間、今の自分が求めているものがそこにある気がしました。現在私はマーケティング部の営業企画チームでリーダーをしていて、主なミッションは営業の支援と業務の効率化。募集当時はチームリーダーではありませんでしたが、顧客対応や社内ポータルの整備、海外パートナーとの調整など、営業を支える立場として“どう伝えるか”や“どうつなぐか”を日々考える中で、問題解決力やファシリテーションスキルをもっと深めたいと思っていたところでした。そして、募集要項に書かれていた“コーチングで人生が変わる”という言葉にも、素直にワクワクしました。」
目指したのは、キャリアアップではなく、新たな視点を得て、自分自身をバージョンアップすること。
小さなざわめきが、大きな一歩につながった。
踏み出すことで見える景色──“人生に効く”コーチング
プログラムは1年間にわたり、月1回の外部コーチによるセッションと、日常的な実践を通して構成されている。中でも印象的だったのが、「1日5分間投稿」と呼ばれるトレーニング。学んだメソッドを日常に落とし込み、継続して実践するための工夫が随所に散りばめられていた。
「最初に教わったのが“試着力”という考え方でした。まずは試してみる。やってみないとわからない。その姿勢がすべての原点でした。」
コーチングは、単なるスキル習得ではなく、自分自身の内面と向き合う営みでもある。自分の行動や選択が結果を変える。マインドが変われば、言葉も行動も習慣も変わる。そして、目指すゴールそのものが変わっていく。
「仕事でも、日々の中でも、意識が変わったと実感しています。何か問題が起きても、問題=チャンス。“チャンスリストが増えた!”とより前向きに向き合えるようになったんです。“これって変われるチャンスだな”って考えると、自然とワクワクしてくるんですよね。」
日々の言葉づかいにも変化が表れているという。
「たとえば以前は『最近忙しくて大変』って言っていたところを、今は『最近大人気なんです!』って言い換えるようになりました。気付けば自然と前向きな言葉が出てくるようになっていて、大きな変化を感じています。」
仕事だけでなく、人生全体が軽やかに、豊かに変わっていく。そんな変化を、彼女は心から楽しんでいるようだった。
加えて、プログラムの意義は個人の変化にとどまらない。コーチングを学んだメンバーがそれぞれの職場で実践していくことで、チームの中に新しい言葉、対話、問いかけが自然と広がっていく。経営層の思いを“自分ごと”として受け止め、組織に自律性と変革力を根づかせていく。その中核を担う存在として、8名の社内コーチが誕生した。
空気を変える、人を動かす
“伝える”から“気づきを手助けする”へ──当事者意識を引き出す会議のあり方
1年間の学びを終えた社内ブレイクスルーコーチ1期生たちは、自分たちが得たものをどう社内に還元していくかを話し合った。そこで生まれたのが、TTS全拠点で行われる「エリアミーティング」において、社内コーチがファシリテーターを担うという新たな挑戦だった。
これまでのエリアミーティングでは、取締役や部長クラスが中心となり、ビジョン・ミッション・バリューを共有していた。そこに、参加者と近い立場の社内コーチがファシリテーターとなり、“問いかけ”と“対話”というコーチングの視点を取り入れることで、一人ひとりが「自分の言葉」で組織の未来を語れる場へと進化させようとしたのだ。
会の冒頭では「この会議で、自分が得たいものは何か?」を会議の参加者全員がチャットで書き出すことからスタート。発言はその後。まず文字にすることで思考が整理され、発言の質も濃くなる。
「チャットで意見を出し合うと、周囲の意見に引っ張られずに、全員の意見が短時間で集まり、“私はこの目的でここにいる”という意識が参加者全員に生まれるんです。呼ばれたから参加するのではなく、“得たいものを手に入れるのは自分自身だ“という自覚が、会議の空気を変えます。」
一体感と対話で、有機的な場をつくる
ファシリテーションにおいて彼女が特に意識していたのは、「空気づくり」と「巻き込み力」。
“8つの合意事項”を全員で共有し、会議中は「枕詞を使わない」「携帯はオフ」「ストレートに答える」といったルールを確認することで、場に集中力と一体感が生まれる。
「発言を促すときも、“○○さん、お願いします”ではなく、“どうぞ”と声をかけていました。みんなが対等な立場で、安心して言葉を交わせるようにしたかったんです。」
表情やうなずき、あいづちにも気を配る。「あなたの話を聞いているよ」という姿勢を、言葉以外の部分でも示すことが、自然と空気をやわらかくする。さらに、意見に対しては即座に判断せず、一度受け止めてから「それはなぜ?」「どうすればできそう?」と問いを重ねる。そうすることで、発言者自身の中に“気づき”が芽生え、周囲の視点も広がっていく。
「問いかけを重ねる中で、参加者の表情が変わっていく瞬間が好きなんです。“あ、自分の言葉で未来を考えていいんだ”と感じてもらえたら、ファシリテーターとしてそれ以上の喜びはありません。」
上下も役職も越えて、ひとつの輪になれる場づくり。社内コーチ達たちがファシリテーターを担うことで、参加者全員が自分もこの場の重要な一員だと意識し、全員で前向きな意見を交わし合う有機的な場となった。
前向きな連鎖が、組織を変えていく
“問題”は伸びしろ──チームに広がるポジティブな変化
エリアミーティングをきっかけに、ブレイクスルーコーチのメソッドが少しずつ社内に広がり始めた。会議の冒頭で「何を得たいか?」を明確にし、ディスカッションでは「どうすればできるか?」という前向きな問いが交わされるようになってきている。課題に対する捉え方が変わることで、会議の空気や参加者の姿勢にも確かな変化が生まれている。
「何を得られたら成功なのか?という視点が定着してきているのを感じます。“問題”を“問題”のままで終わらせず、“どうすれば実現できるか”に転換できる人が増えてきました。」
その変化の手応えは、社内の空気だけではなく、彼女自身の意識にも表れている。
「以前からポジティブな方ではあったと思いますが、今は“問題はチャンス”と自然に思えるようになりました。相手の言葉にじっくり耳を傾け、問いかけながら本音や想いを引き出していく。そんな関わり方を意識するようになったのも、コーチングの学びがあったからです。」
相手の力を引き出す意識が身についたことで、チームリーダーとしての自信にもつながった。
「一人ひとりが、100%の可能性を持っている。その可能性を信じて、気づきを促す存在でありたい。」
傾聴、承認、質問。彼女がメンバーと向き合うときに大切にしているのは、この3つの基本だ。アドバイスを押しつけるのではなく、相手の言葉を引き出し、思考を整理し、自ら答えにたどり着けるよう寄り添う。その姿勢は、自然とチーム内の信頼関係を育んでいった。
「仕事を含む人生全体が、よりポジティブに、そして楽しくなったという感覚があります。」
今では、周囲の変化を心から喜びながら、自分自身も前向きに学び続けている。
挑戦は続く──新たな社風をつくる一員へ
2025年現在、TTSでは第2期生の社内ブレイクスルーコーチの募集が始まっている。
今度は彼女ら1期生が“講師”となり、次に続く仲間を育てる番だ。
「教える立場になることで、また新しい気づきがあるはず。“わかる”と“できる”の違いに向き合いながら、自分自身も成長していきたいと思っています。」
いま目指しているのは、コーチングを“スキル”ではなく、“文化”として組織に根づかせていくこと。チームリーダーやプロジェクトマネージャーなど、現場の中心で人と関わる人たちにこそ、コーチングの力を届けていきたいと考えている。
「1人1人が前向きに課題を捉えられるようになれば、チーム全体のエネルギーが変わってくる。そんな職場づくりを、これからも仲間と一緒に目指していきたいです。」
“やらされる”から“自ら動く”へ。この気づきが、やがて大きな風土をつくる。
その輪の中心に、彼女のような存在がいることは、何よりの希望だ。
取材を終えて|グループ広報部より
彼女には常に前向きなエネルギーが宿ります。「問題はチャンス」という言葉の裏には、日々の小さな実践と、自分自身への問いかけの積み重ねを感じました。
今回特に印象的だったのは、彼女自身の変化がチームや組織全体に波及していること。“伝える”から“気づきを手助けする”へ。“話す”から“引き出す”へ。そんなファシリテーションの力が、会議や対話の場を変えはじめています。社内で育ったコーチたちが、日々の現場から組織を動かしていく──そこに、東京貿易グループのコアバリューである「全員経営の精神」が重なって見えました。
TOMAS PALETTEは、これからも現場で芽生える意識の変化と、コーチングが組織文化として育っていく過程を見つめながら、その先に続くグループの未来と成長を描いていきます。
東京貿易グループでは、さまざまなキャリアの機会があります。ぜひ一緒にはたらいてみませんか?お気軽にこちらからお問い合わせください。
あわせて読みたい