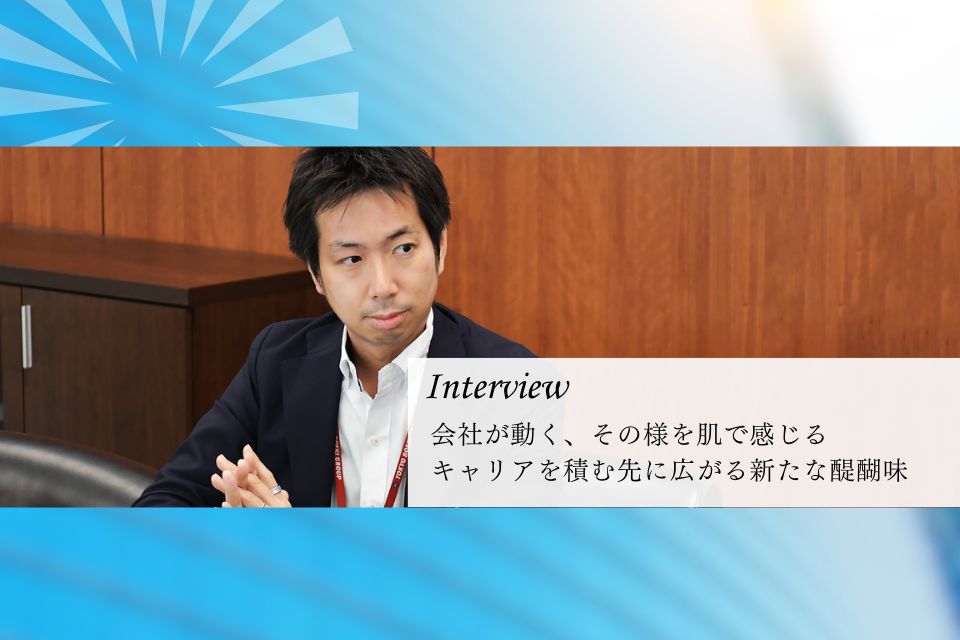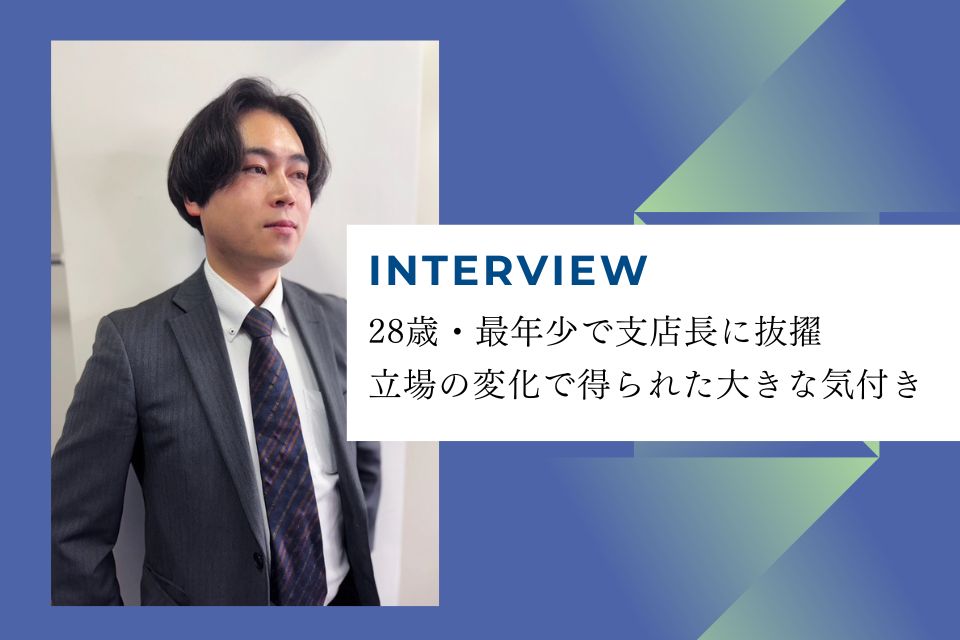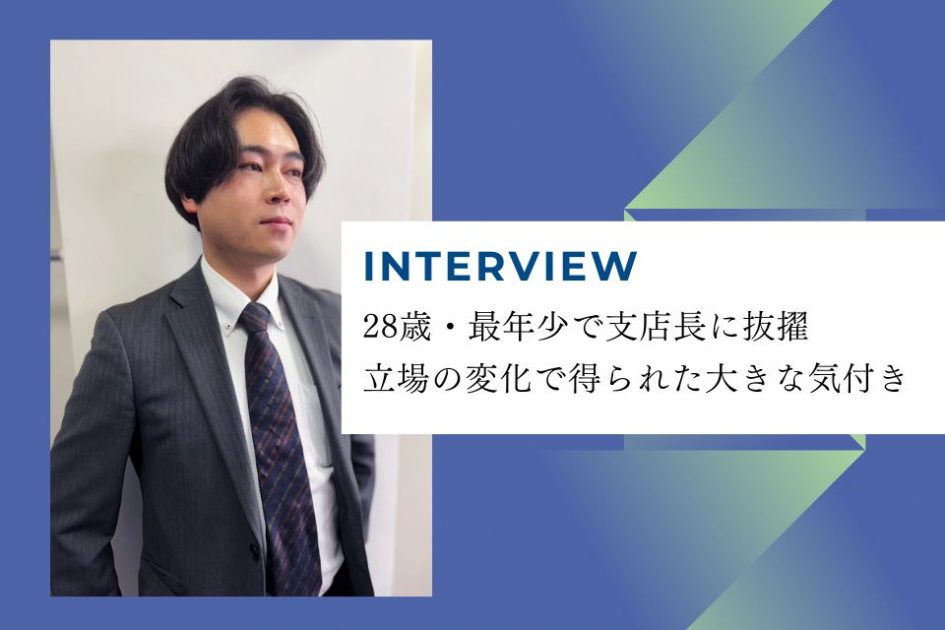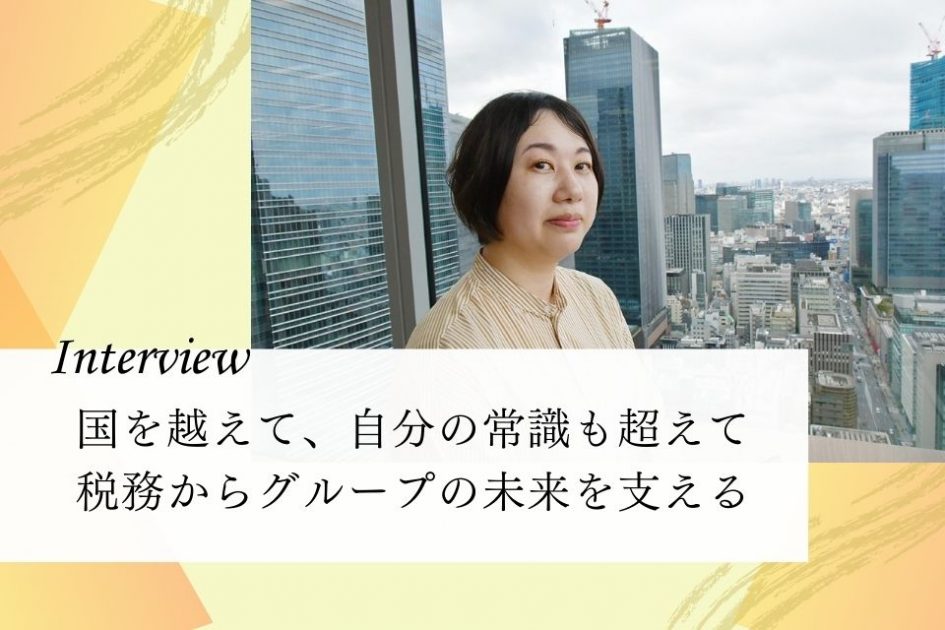社員インタビュー:会社が動く、その様を肌で感じるキャリアを積む先に広がる新たな醍醐味
― キャリアアップの節目で自分が何をすべきか考え、フィールドと視野を広げる
今回ご紹介するのは、株式会社ティービーアイ(以下 TBE)IT課 課長の谷本俊朗さん。営業職からシステム設計と職種を変え、それぞれの場面で成果を残し、2024年の4月からは、IT課の課長に就任。直属の部下や共にプロジェクトを推進するメンバーからも「こちらの意見をいつも大事にしてくれる」「周りを伸ばすことを常に考える人」と厚い信頼を得る谷本さんは、管理職になり東京貿易グループ(以下 TB-GR)の横断プロジェクトの主要メンバーになるなど、活躍のフィールドをさらに広げています。
様々なポジションで活躍してきた谷本さんが、それぞれの時期にどのような思いで仕事をしてきたのか、キャリアアップを経て得たことは何か。谷本さんの歩みを振り返りながら、これまでの活躍の裏にある思いや、キャリアアップにおける視野の変化について迫ります。
この記事でわかること
・TBEでのキャリアステップ
・各ステージにおける仕事のやりがい
・管理職の仕事の面白さ
・キャリアアップによって得られる成長・視野の広がり
-
PROFILE

谷本 俊朗 Toshiro Tanimoto
株式会社ティービーアイ
総務部 IT課 課長
2007年に中途入社。セキュリティカメラを中心とするトータルカメラソリューションサービスの営業を経て、2017年よりIT課へ異動、社内システムの設計業務に携わる。2024年4月には同部署にて課長に就任。TB-GR横断のDX推進プロジェクトのメンバーとしても活躍。社内・プロジェクト内からも多くの信頼を集め、管理職として今後の活躍が大きく期待される存在。
目次
・根本にある価値観は「相手の声を聞き、自分の最善を出す」
・営業、システム設計、課長。それぞれの仕事で学んできたこと
・社員の声、会社の声。互いに意見を交わし活かせる会社へ
・コラム|オーケストラに所属しフルートを演奏
・取材を終えて|グループ広報部より
根本にある価値観は「相手の声を聞き、自分の最善を出す」
人生に息づくオーケストラでの経験
社会人になり何年もたちますが、自分の根本にあるのは「オーケストラ」です。中学の頃から30年以上フルートを続けて、現在もオーケストラ団体に所属。年に1度は演奏会に参加しています。
様々な楽器を持った数十名もの演奏者が一堂に会し、一つの音楽を奏でるオーケストラ。仲間の音を聞きながら、自分がどんな音を出すべきか。それぞれの音を調和させ、心をひとつにすることで素晴らしいハーモニーを生み出すことができるオーケストラに魅了されてきました。
そしてこの考え方は、私の人生に息づいていて、仕事にも活かされています。
相手が何を考えているか、何に困っているのか、どうしたいと思っているのか。そこにしっかりと耳を傾け、自分がすべきことをやっていく。そうやって仕事にも取り組んできました。
社会が必要とするものを届ける仕事を
大学は経営学部。就職活動では、セキュリティ関連の会社に興味を持ち、防犯カメラの販売代理店に内定しました。記録媒体がビデオテープからハードディスクへと移行していくタイミングでもありましたし、安心安全というものは、社会的に常に求められるもの。セキュリティ分野は今後ますます伸びていくと感じ、将来性が決め手となりました。ここでは新規開拓の営業を経験し、営業としての第一歩を踏み出しました。
入社し3年ほど経過した時、先にTBEへ転職した先輩から話を聞く機会があり、興味を持ちました。TBEは販売代理店の機能も持ちますが、それに加え、メーカーの機能も持つ“メーカー商社”でもあります。もっとこういう機能があったらいいのに…という声をものづくりに反映させて、よりよい製品を世に出すことに携われる点に魅力を感じました。そして、TBEなら自分を成長させられると思い、転職を決意しました。
営業、システム設計、課長。それぞれの仕事で学んできたこと
営業の仕事:お客様の求めることにいかに早く応えられるか
TBEに入社後は、営業本部セキュリティシステムという部署に配属。監視カメラを扱う代理店に対し、TBEのカメラシステムソリューションを提案する仕事です。一口に監視カメラといっても用途は様々。オフィスや住居のセキュリティシステムから、ショッピング・レジャー施設の人の動きを記録・分析するマーケティングや、台風や大雨の時には川の水位の上昇を監視する防災にも活用されています。それぞれの目的を見据え、どのカメラを使用するのか、カメラから正しい情報を取得するためのシステムなど幅広い知識も必要となります。
さらに営業としては足を使うことも不可欠。設置するのは整備された場所ばかりではありません。たとえば屋外の駐車場にセキュリティカメラを設置するケースでは、何もないところにまずポールを立て、設置ボックスをつけます。となると施工の知識も必要です。配線や風雨への対策など、現場に立ち合い、設営や配線処理も学びました。自分の知識量と経験値を高めることで、お客様への対応力を身に付けてきました。
そして最も心がけていたことは、「スピード」です。お客様から連絡が入るということは、何か困りごとがあるということ。状況をできる限り詳細にヒアリングし、いつ頃復旧できそうかの目安や対処の方法など、営業である私ができる限り早く答えられることが、お客様にとっての安心。製品知識だけではなく安定稼働のための知識こそ、営業力につながると信じてきました。
営業とは、お客様から見るとTBEの最前線。お客様の求めることをしっかりとつかみ取り、スピーディーかつ的確に応えていくことで信頼関係が築かれていきます。これは営業の基本ですが、全ての仕事の基本でもあると今も思っています。
システム設計の仕事:営業の経験があるから集まる現場の声を、活かす
TBEに入り10年経過した2017年、IT課に異動となりました。社内情報システムの管理のほか、社内用販売管理システムを刷新するプロジェクトにも携わることになりました。営業からシステム設計へ行く人は珍しいのですが、より使いやすい社内システムを構築するために、営業現場での経験がある人を入れようという理由もあったのかと思います。
これまでと比べると、仕事内容は激変。お客様先へ訪問しカメラシステムソリューションを提案するという仕事から、社内のシステムの課題を洗い出し、新たなシステムを構築するという仕事へ。大きな変化に最初は戸惑いもありました。ただし、10年間、営業の最前線でやってきた経験は必ず活かせるはずという思いもありました。営業としての経験に加え、自分の強みとなったのは「社内のつながり」でした。10年の社歴があるからこそ、社内を見渡すと顔見知りの社員が大勢います。「現状のシステムで使いにくいと感じるところはどこか?」「どういう情報があるとアクセスしたいと思えるか?」など、要所要所でヒアリングを重ねることができました。現場の声はニーズが凝縮されているからこそ、できるだけ多く集めて、その声がしっかりと反映された社内システムを作り上げよう、と目標が定まりました。
システム設計の仕事の面白さは、社内への影響範囲の大きさです。営業の時は、自分が相対するお客様のことに集中して考えていましたが、システム設計の場合は、現場で働く社員の声を拾ってシステムに反映することで、現場の誰か1人の声が社内に波及し、会社全体の効率化や売り上げ向上につながっていく。その広がりに、非常にやりがいを感じました。
管理職の仕事:社員と会社をつなぎ、未来をつくる
そして、2024年4月。IT課の課長に就任しました。課長になると、これまでとは入ってくる情報が大きく変化しました。事業戦略や制度改革など、出席する会議の議題も、目線は会社。TBEとして、TB-GRとしてどう動いていくかに直接関わるようになり、見える世界も変わってきました。
ただし、私も課長になってまだ1年ほど。だからこそ感じられることですが、会社としての動きが、働く社員に浸透しているかといえば、できることはまだまだあります。
中長期的な目線で会社として大きな目標があり、それを実現するために、たとえば私がみているIT課なら、2年後3年後どうなっていかないといけないのか。個々人の目標に置き換えた時に、社員は何をしていくべきなのか。そのハブとなり、1人1人が抱いている仕事の目標や望む働き方とすり合わせ、落とし込んでいくことが、管理職としての自分の役割なのだと実感しています。
管理職という仕事の醍醐味は、「部下の力を引き出すこと」。自分とは異なる考え方を持つからこそ、仕事への考え方を聞いても発見がありますし、自分がアドバイスすることで想像以上の成長も見られる。だからこそ、どんな意見にも耳を傾けるということは心がけていきたいですし、部下が持つ無限の可能性をひらいていけるような存在になることが目標です。
また、「会社の成長に寄与できること」も、もう一つの醍醐味です。現場には、会社を動かしていく上で有益な意見がたくさん散らばっています。その意見を具体化し、実現するように働きかけることができるのも管理職だからこそ。私の所属するIT課でも、部下たちが抱く大小様々なアイディアを新たに構築する社内システムに取り入れるべく動いています。社員から出た声をそこで終わらせるのでなく、会社を動かす原動力にしていく。そんな役割を自分が先頭に立ってやっていきたいと思っています。
社員の声、会社の声。互いに意見を交わし活かせる会社へ
グループ横断プロジェクトにも参加
課長に就任する少し前から、TB-GR横断の“DX推進プロジェクト”というプロジェクトチームにも参加しています。これは、TB-GR全体のデジタルリテラシーを高め、業務の効率化を図り、本質的な課題に向き合うことに注力することを目指したプロジェクトです。東京貿易ホールディングス(TBH)のDX推進部を中心に、TB-GRの各社からメンバーが集まり、TBEの代表として私が参加しています。
デジタル技術を駆使し、業務をどう効率化できるのか、逆にどこに時間を割くべきかというのがテーマになるので、今までに自分の中になかった観点に気付き、物事の考え方を見直すきっかけにもなっています。
また、TB-GR各社からさまざまな職種・立場の人が集まり意見を交わすので、仕事に対する考え方や文化・風土の違いも勉強になります。会社を超えたつながりができることで、発想も視野も広がります。
こういった取り組みが動いていることに、TB-GRが変わろうとしている意志を感じます。その最中でTBEの代表としてプロジェクトに参加できることはとても光栄です。営業・システム設計・課長と、様々な仕事・ポジションを経験してきたからこそ、プロジェクトにとって役立つ意見を発信していきたいですし、ここで得たことをTBEにも持ち帰り浸透させていきたいですね。
管理職という仕事の面白さを、体現したい
管理職になって1年経とうとしていますが、「想像以上に面白い」というのが率直な感想です。人の力を引き出すこと、会社を動かすことが管理職の仕事。部下の成長を間近で見たり、会社を動かすポジションになったり、自分自身の視野もぐっと広がっています。管理職とは、人と会社の成長を通し、自分自身を成長させていける仕事。私自身がこの仕事を楽しみながら、その姿を部下にも見せることで、管理職の面白さを伝えていきたいです。
そしてもうひとつ。実現したいのは、より風通しのよい風土にしていくこと。仕事のやりがい、働きやすさ、チャレンジしたいこと。大小問わず、1人1人が意見を自由に交わせる環境、そして多様な意見が活かされていく組織。この理想を叶えるために、これからも力を尽くしていきたいと考えています。
取材を終えて|グループ広報部より
今回のインタビューでは、2024年に管理職となり、新たなフィールドへ踏み出した谷本さんにお話をお聞きしました。
「管理職になったことで、会社の動く方向をダイレクトに知り、見える世界が大きく変わった」と語る谷本さん。今まさに大きく変化するTB-GRの動きを確実に部のメンバーに伝え、その上で1人1人の声に耳を傾け、モチベーション向上や成長を促す姿に、谷本さんの個性が光る管理職としてのあり方を感じました。TB-GRの行動指針である「共創力」を体現しながら、「闊達」に働ける環境を見据え、谷本さんがひたむきに働く姿も強く印象に残りました。
谷本さんが果敢に次のステージへ挑む姿、そして、TBEで働く1人1人の声がどのように形になっていくのかを、私たちも注目していきたいと思います。
東京貿易グループでは、さまざまなキャリアの機会があります。ぜひ一緒にはたらいてみませんか?お気軽にこちらからお問い合わせください。
あわせて読みたい